目次
はじめに
トッドの歴史観の基礎には、歴史を動かすのは人間の集合的心性(メンタリティ)である、という命題があります。
*由来などはこちらをご覧ください。
心性に影響を与える要素はいろいろありますが、もっとも本源的な規定力を持ち、かつ、もっとも持続力が高い(容易に変化しない)のが、家族システムの影響である。この事実を発見し、両者の関係性を具体的に示してみせたのが、トッドの最大の功績といえるでしょう。

本講座は、トッドのこの見解を受け入れ、「家族システムの変遷-国家とイデオロギーの世界史」などの連載をしているうちに、「それぞれの家族システムには、それぞれの基幹的価値(core value) のようなものがあるのではないか」と感じるようになりました。
*トッドは、親子関係から「権威/自由」、兄弟関係から「平等/非平等・不平等」の各イデオロギーを読み解きますが、私の仮説は、その組み合わせに意味を見出そうとするものといえると思います(トッド自身もどこかでそんなことを考えているような気もします)。家族システムの進化は(偶然ではなく)必要に迫られて発生し、新たな国家形態を生み出すものなので、親子関係・兄弟関係の組み合わせが何らかの言語化可能な「価値」につながっていると考えるのは、それほど無理な推論ではないでしょう。
表にしてみたのがこちらです。

では、空欄の「識字化した(=近現代の)核家族」の部分には、どんな価値が入るでしょう。
家系の永続も、国家安寧も、世界平和も気にしない。それでいて、自由には固着する核家族。
彼らが率いた世界がどんな世界だったかはすでに見てきましたが、その「抗争と掠奪」(そして「暴力と殺戮」‥‥ )の世界は、どんな価値・メンタリティの上に成り立ったものなのか。
それを解明しよう、というのが、今回のテーマです。
◉最終回のテーマは「近代のメンタリティ」の解明
【注意】「彼ら」とは何か
この連載で、私はしきりに「彼ら」「彼ら」と書いてきました。そして、今回の課題は、その「彼ら」のメンタリティの解明です。しかし、そもそも、「彼ら」って誰のことなのでしょうか。
ここで、是非とも思い出していただきたいことがあります。それは、トッドの専門である人類学は、科学の視点から人類を研究する学問であるということ、そして本講座もまた「人類を生物種の一種として眺める」視点に立っている、ということです。
このウェブサイトを始めた初期の頃、番外編として「文明以前の人類史ー人間はどういう生物か」という講義をお届けしたことがあります。このとき私が提示した仮説は次のようなものでした。
*時間が経って頭が整理されたので、多少言葉を変えたり補ったりしています
- 人間は「社会」というフィクションの中で生きるように進化した生物である
- 人間は「社会」の構築・適合のために「人間らしさ」を身につけた
- 「人間らしい」脳の機能(理性や感情)の最重要の目的は「社会を作り社会に適合すること」なので、その働きは通常理解されているほど「自由」ではない
そのときにも(おずおずと‥)書きましたように、本講座は、エマニュエル・トッドの理論は、こうした人間の心の仕組みの一端を解明するものであると考えています。そこで、彼の発見を参考に、上記の仮説に続けて、いくつかの仮説を加えてみましょう。
- 社会構築の母体は、集合的心性である
- 家族システムが表現しているのは、人間が構築する社会の型である
- 人間の心と社会は、集合的心性を介して、双方向のベクトルでつながっている
- 集合的心性は、社会を構成する個々人の心の集合体である。したがって、社会の特徴(個性)は、社会を構成する人間の多くが共通に保有する心的成分によって形成される
- 社会を構成する個々人の心には社会の型(家族システム)に合致しない成分も多く含まれており、社会の型の相違に伴う個々人の相違はわずかである。また個々人の心は、異なる社会への適応が必要となったときには、比較的容易に変化する
- 集合的心性の特徴(社会の個性)は、社会の構成員の心だけではなく、歴史的に形成された習慣や制度に刻み込まれているため、変化は緩慢で漸進的である。
このウェブサイトで、私が用いる「彼ら」の語は、たいていの場合、この「集合的心性」を指しています。
集合的心性とは、個々人の心の集合体ですから、社会の成員一人ひとりと無関係ではありません。
では、一人ひとりの人間が、集合的心性を変えることができるか、といえば、一人の行動、一人の心の変化が、実際上、目にみえる変化をもたらすことができないことは明らかです。
集合的心性から見れば、一人の人間の心はまさに大海の一滴。その上、その大海には、いま生きている人間の心的成分だけでなく、制度や慣習といった形で、歴史を通じて選りぬかれた集合的心性の粋(すい)が流れ込んでいるのですから。
例えば、直系家族の日本に生まれ育った一人の(平均的な)人間の心と、核家族のイギリスに生まれ育った一人の(平均的な)人間の心は、そんなに大きくは違いません。日本の人の中にも、核家族っぽい要素はあるし、イギリスの人の中にも、直系家族っぽい要素もある。
それにもかかわらず、その「一人」がたくさん集まって社会を作り、歴史を重ねると、そこには、簡単には変わらない、明確な特徴が刻まれてしまう。それこそが、社会というものの、厄介で、かつ、おもしろいところなのです。
今回より、私たちは、「抗争と掠奪」「暴力と殺戮」そして「おかねがすべて」の時代を作ることとなった(識字化した)核家族のメンタリティの解明を目指し、探究を始めます。ここでも、観察の対象となるのは、もちろん、集合的心性です。
参加者の皆さんは、「彼ら」を社会を構成する個々人と同視して感情的になったり、はたまた、真相の究明を躊躇ったりすることのないよう、肝に銘じてくださいね。
銘じましたか?
はい。それで準備はOKです。
早速、本編の探究を始めましょう。
◉「彼ら」とは、一人ひとりの人間ではなく、集合的心性(メンタリティ)のことである
*集合的心性についてもう少し説明がほしい方は、下の2つの記事をご参照ください(↓)。
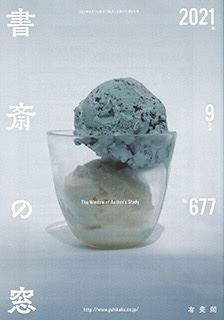
君たちはどう生きるか(連載 平らな鏡で世界を見れば⑧ 最終回)
書斎の窓 2021年9月号(No677) 有斐閣
原初的核家族のメンタリティ:未開人は暴力的か?
近代の(絶対)核家族と原初的核家族には、「権威・平等の双方を欠く」という共通点があります。

この点を頭に入れて、「なぜ近代はこんな時代になってしまったのか・・」と考えると、最初に思い浮かぶのは、つぎのような仮説だと思います。
仮説① 「抗争と掠奪」「暴力と殺戮」「おかねがすべて」の近代は、未開人に酷似する(識字化した)核家族の野蛮なメンタリティによってもたらされたものである
なかなかもっともらしい仮説ですけど、この仮説に依拠して検討を進めるには、その前に、確かめておかなければならないことがありますね。
そう、未開社会の人々のことです。
未開社会の人々は、家族システムを構築していなかったので、権威も平等も持たなかった。だからといって、彼らは「野蛮」で、争い、奪い、殺し合ってばかりいた、と考えてよいのでしょうか?
狩猟採集社会の人類の暴力性については、比較的最近になって、改めて議論が活性化しているらしく、興味のある情報を得ることができました。
まず、20世紀を通じて、考古学などの研究者の間で主流であった見方は、狩猟採集社会は比較的平和であった、というものだそうです。
*狩猟採集社会では集団的暴力(戦争)は稀だったが、農耕の開始による人口増加、土地や水の争奪、社会の複雑化などの影響で、戦争が頻発するようになったのだ、という理解です。
ところが、21世紀に入ろうという頃から、「いや、違う」という人たちが現れます。彼らは「未開の人類は非常に暴力的で、戦争も頻繁だった。むしろ、現代の人類の方が平和的なのだ」と主張するのです。
考古学者の松本直子さんに教えていただきましょう。
‥‥近年、むしろ文明や国家が発達する以前の社会は暴力的であり、国家の成立によって戦争は減少しているという見方が台頭してきた。平和で豊かな狩猟採集民というイメージは、イデオロギー的な幻想であり、実態はむしろ戦争の世紀と呼ばれる20世紀よりも戦死者の比率が高かったとする説が複数の研究者によって唱えられ、世界は国家による統制により平和になってきているという主張が多く見られるようになった(Keeley 1996, ガット2012, ピンカー2015)。さらに、頻繁な戦争状態がヒトの特性である利他的な性質の進化を促したとする説も出されている(Bowles 2009)。
松本直子「狩猟採集社会における戦争ー集団間の暴力を促進/抑制する要因について考えるー」考古学研究65巻3号(259号)(2018年12月) 22頁
*名前が上がっている研究者が全員核家族地域の出身者であるのは興味深いです(Laurence H Keeley(アメリカ)、Azar Gat(イスラエル)、Steven Pinker(アメリカ)、Samuel Bowles(アメリカ))。
狩猟採集時代の人類(原初的核家族)は、近現代の人類と比べて、平和的だったのか、暴力的だったのか。どちらなのでしょうか。
松本さんによりますと、これまでのデータを総合すると、軍配は前者の「どちらかといえば平和だった」説の方に上がるようです。
「未開人は暴力的」派の人々も、もちろん、根拠となるデータを示しているのですが、彼らのデータの用い方には偏りがあるようなのです。
ピンカーのデータについては、松本さんご自身も、次のように指摘しておられます。
戦争による死亡率平均14%の産出の根拠としてピンカーが用いている先史時代のデータは、時代も地域もさまざまな21か所の遺跡から得られたものであり、東アジアのデータはおそらく英語であまり公表されていないため全く使われていない。また、民族誌における戦争による死亡率についても、やはり平均14%程度と算出されているが、民族誌に基づくデータは、たとえ狩猟採集民のものとされていても、さまざまな形で農耕社会との接触があるケースがほとんどであり、先史時代の狩猟採集社会と同等に扱うことはできない。‥‥データに偏りがあるという批判はすでになされており(Fry 2013, Fry and Soederberg 2013)、より体系的・網羅的なデータによって検証することが求められている。
松本直子「狩猟採集社会における戦争ー集団間の暴力を促進/抑制する要因について考えるー」考古学研究65巻3号(259号)(2018年12月) 26頁
そこで、東アジアのデータとして、日本列島で出土した縄文時代と弥生時代の遺跡のデータを付け加えて検証を行った松本さんは、つぎのような結論に達しています(松本さんの言葉を借りながら私の言葉でまとめます)。
遊動的なバンド社会に限れば集団的な暴力はほとんど見られず、また、体系的にデータを集めると受傷率はそれほど高くない。したがって、先史時代の狩猟採集社会で戦争が頻発していたとは考えられない。
松本直子「狩猟採集社会における戦争ー集団間の暴力を促進/抑制する要因について考えるー」考古学研究65巻3号(259号)2018年12月 参照
集団的な暴力(戦争)は、人類史の初源から頻発しているわけではなく、ある段階で発生し、拡大したとみるべきである。
そういうわけで、本講座は「狩猟採集社会に暮らした原初的核家族は、それほど暴力的ではなかった」という立場に立ち、近代の暴力性の原因を「未開人類似の野蛮なメンタリティ」に求める仮説①を「不採用」とさせていただきます。
◉未開社会の原初的核家族は、さほど暴力的・好戦的ではなかった
◉近現代が「抗争と掠奪」「暴力と殺戮」の時代となったのは、「未開人類似の野蛮なメンタリティ」のせいではない
エマニュエル・トッドとの対話ー人間集団には「敵」が必要なのか
(1)核家族か人類か
では他にどんな仮説がありうるか‥‥と考える私の中では、近現代の暴力性が、何らかの形で、それを率いた西欧の核家族性と関わりがある、ということは大前提です。
しかし、近現代のある種の「野蛮さ」を核家族の特性に結びつける私の立場には、見過ごすことのできない有力な反対者がいるのです。
その人とは、なんと、エマニュエル・トッド。
いうまでもないことですが、私たちに、西欧近代を率いた核家族と、狩猟採集民との近接性を教示してくれたのはトッドです。
彼は、『我々はどこから来て、今どこにいるのか』(文藝春秋、2022年)の中で、狩猟採集時代の人類と核家族(とくにアングロサクソン)の類似性を論じており、同書(日本語版)の上巻・下巻の副題はそれぞれ、
「アングロサクソンはなぜ覇権を握ったか」
「民主主義の野蛮な起源」。
これに対するトッドの答えは、
「アングロサクソンが覇権を握ったのは、彼らが原初の狩猟採集民と同じメンタリティと持っているから」
「民主主義の起源は、メンバーが集会を開き、合議し、その集団に関わる決定を行なっていた原始社会の意思決定にある」。
彼ら〔アメリカ人〕は、ほとんどまったく洗練されていないからこそ、先を行っているのである。ほかでもない原初のホモ・サピエンスが、あちこち動き回り、いろいろ経験し、男女間の緊張と補完性を生きて、動物種として成功したのだ。
上・351頁
西欧近代の西欧近代たるゆえんを、核家族のメンタリティに求める彼の立場は、ここまでは、われわれの想定とほぼ同じです。しかし、暴力性ということになると、彼のトーンは少し変わります。
トッドは、現代の人間が、他者を敵視し、戦争を厭わないことの淵源を、狩猟採集民のメンタリティに求めます。その上で、彼は、そうしたメンタリティを、「核家族の個性」ではなく、「人間の本性」。つまり、全人類に共通の属性と見るのです。
*政治的配慮である可能性がゼロではないと思いますが、一応、そうではないものとして話を進めます。
◉トッドは、近現代の暴力性の基礎にある狩猟採集民のメンタリティを「人間の本性」と捉えているようだ
(2)「人間の本性」とは?ートッドの立論
では、彼の見る「人間の本性」とはどのようなものなのか。一言でまとめるとこうなります。
人間は、他者に対する敵意を共有することなしに、集団としてまとまることはできない(敵意原則)。
*便宜上「敵意原則」と名前を付けます。
このような理解を導くために、彼が大いに参照しているのが、スコットランド啓蒙期の歴史家・哲学者、アダム・ファーガソンです。
*トッドは彼を「おそらく思想史上初めて、民族学的に収集された具体的データを人間についての施策に組み込んだ」(上・152頁)人物として高く評価しています。彼が主に用いたのは、北米インディアンに関するデータだったそうです。なお、私たちは、このデータが(先ほどお教えをいただいた)松本さんのいう「たとえ狩猟採集民のものとされていても、さまざまな形で農耕社会との接触があるケース」にほかならないことに注意しましょう。
アダム・ファーガソンという人が何をいっているのか。トッドによる引用を少しご紹介しましょう。
《 近年の発見によって、我々は、地球上のありとあらゆる状況における人類の暮らしを知ることとなった。広く大きい大陸で、交通が開け、民族や部族の連携が容易な環境に暮らすものがあれば、山や大河、入江に周囲を囲まれた狭小な地域に暮らすものもある。小さな島で、住民たちは容易に集まることができ、そうした協力関係を活かして生活するものもある。しかし、そうしたすべての状況において、人類は、等しく、複数の集落に分かれ、〔他と区別するための〕名前を付けた共同体を組織して暮らしていた。「同胞」や「同郷人」といった呼称は、対立概念である「よそ者」「異郷人」なしには、用いられることもないし、意味を持ち得ないものであろう。》
《これらの観察はわれわれ人類を告発し、人間というものについて好ましくないイメージを生み出すように思われる。通常、戦士たちを自国の防衛に立ち上がらせるのは、高潔寛大な無私の感情であると考えられている。それらは、人類が持ちうる最も好ましい性質であるとも考えられている。[これらの観察によれば]こうしたものが、すべて、他者を敵とみなすという人類全般に見られる行動規範に還元されてしまうのだ。国家間のライバル関係がなければ、そして実際に戦争を遂行することがなければ、市民社会が存在する目的を見出すことも、形になることも、おそらくできなかったであろう。》
上・152-153頁(日本語版がベースですが、英語版を参照して翻訳には大いに手を入れました)
ファーガソンに対するトッドのコメントはこうです(↓)。
この〔ファーガソンの〕捉え方がいかに生々しく現代に通じているか、われわれは、ヨーロッパのネイション間の平和が持つ社会解体的効果を確認することをとおして痛感する。ファーガソンを読んだあとでよりよく理解できるのは、現代の先進諸国の社会が、自らのバランスを取り戻すために、国内でイスラム教徒たちを独特の集団として意識したり、対外的にはロシアを悪魔化したりする必要に駆られているということだ。突き詰めれば、そのバランスは諸国家の和解によって脅かされているのである。米国で黒人たちがひとつの集団として切り離される状況が永く続くのも、人類固有の同じ論理に起因している。
集団の一体性は、他の集団への敵意に依存する。内部での道徳性と外部への暴力性は機能的に結合している。したがって、外部への暴力性のあらゆる低下は、最終的には、集団内で道徳性と一体性を脅かす。平和は、社会的に問題なのである。
こうしてトッドは、ファーガソンの観察を受け容れ、以後「人間は相互に他の集団を敵視することで集団としてのアイデンティティを形成する生物である」という命題を公理(自明の真理)として採用する、と宣言するのです。
‥‥肝腎なのは、どの集団にも、他の集団との関係に依存しない絶対的なアイデンティティなど存在しない、ということを理解することなのである。フランスがフランスとして本当に存在し始めたのは、14世紀におけるイギリスとの紛争によってだった。米国の白人が白人として存在しているのは、黒人との関係においてだけだ。古代ギリシア人がギリシア人だったのは、現在の「野蛮人」に通じる「バルバロイ」〔訳の分からぬ言葉を話す者〕という呼称で呼ばれた他民族との区別においてだけだった。アテナイ人のアイデンティティはスパルタ人との対抗関係に、キリスト教徒の集団としてのそれは異教徒およびユダヤ教徒との違いに依存していた。たしかに人間社会はさまざまで、経済システム、家族構造、宗教的信仰、政治組織のいずれを見ても、それぞれに固有の性格がある。しかし、どの社会も、外部の指示対象‥‥なしには考えられないし、記述され得ない。外部の指示対象が、相互影響や拒否の長年にわたる絡み合いの中でそれぞれの社会の性格の定着に寄与するだけでなく、各社会の内的一体感の醸成や、外部もしくは内部の「他者」に対する集団の連帯感の活性化を可能にするのだ。いかなる絶対的アイデンティティも存在しない。ホモ・サピエンスという種において、集団のアイデンティティはつねに相対的である。
◉トッドは、敵意原則(「集団の一体性は他の集団への敵意に依存する」)を人間の本性(全人類に共通の属性)とみなす
(3)トッドへの反論
①家族システムの進化とは何か
本講座は、フランスはイギリスとの紛争(百年戦争ですね)によって初めてフランスになった、というトッドの見立てには賛同します。アメリカの白人は黒人、古代ギリシャ人は「バルバロイ」、アテネはスパルタ、キリスト教徒は異教徒やユダヤ人という「敵」がいたから、集団としてのアイデンティティを確立できたという点にも、異論はありません。
しかし、これを、「経済システム、家族構造、宗教的信仰、政治組織」の性格とは無関係の、すべての人間に共通の性質であるとする彼の推論には、論理の飛躍があります。
まさか、トッドが気づいていないはずはないと思いますが、彼が挙げている事例はすべて(トッドの仮説によれば)核家族のものなのです。
*「キリスト教徒」に関しては想定されている時代や状況がわからないので確言できませんが。
われわれは、トッドに学ぶ学究の徒ではあっても、トッド信者であってはなりません。うっかり彼に追従することなく、しかと検証してまいりましょう。
*トッドが無造作に「どの社会も、外部の指示対象‥‥なしには考えられない」と断言してしまうのは、それが彼自身の素朴な感覚と合致しているからではないか、と私は疑っています。
ファーガソンが観察した原初的核家族の人類は、家族システムの進化を経験していない「システム以前」の人々です。したがって、彼らの行動がホモ・サピエンスの初期状態を示しているという点に、大きな誤りはないでしょう。
*ただし、前節(2)の注にも書いた通り、このケースが「農耕社会との接触」が想定されるケースであることには注意が必要です。
トッドは、ファーガソンの観察による原初的核家族の行動原理(「集団の一体性は他の集団への敵意に依存する」)を、家族システムその他の社会構造を問わず、全ての人類に妥当する公理であると断定します。
このとき、彼は、家族システムの進化には、始原的人類が持つ(とされる)「敵意原則」を修正する力はない、と宣言していることになるのですが、本当にそうなのか。
私がトッドに問いたいのはこの点です。
◉トッドが参照している事例はすべて核家族の事例である
②文明の誕生
メソポタミアに最初の国家(都市国家)が生まれたときのことを考えてみましょう。
人類がメソポタミア南部に定住を始めたのは前5500年頃、前3000年紀に、ウル、ウルク、ラガシュといった都市国家が誕生します。


都市国家の誕生は、文字、王、官僚、軍隊、宗教、法が生まれたのとほぼ同時です。つまり、この時期に、現代に連なる「文明」が一気に開花していくわけですが、一体何がこの「文明化」をもたらしたのか。
親族関係の体系化(家族システムの成立)です。
それまでは未分化で、柔軟性を最大の特徴としていた人間集団は、定住し、人口を増やし、「満員の世界」を迎えたとき、長子相続制(=直系家族)のルールを編み出します。
長子相続制(=直系家族)の完成によって、親子をつなぐ縦の絆は、家系をつなぐ一本の線となり、親から子(長子)、子から孫(長子)へと連綿と受け継がれることになる。社会の中に、確固たる縦型の権威の軸が据えられるのである。
https://www.satokotatsui.com/birth-of-state/
この「縦型の権威の軸」が、文字、国家、王家、官僚制度、国家的宗教、法の成立を可能にした、というのが、私が自信をもって提示する仮説です。
*詳しくは以下の記事をご覧ください。
*「権威」の働きについては、次の記事もおすすめです。
この仮説によると、国家という「人間の集団」は、人口が増え、密度が上がった世界で、人間が永く平和的に共存していくために生まれたことになります。
人類は、「満員の世界」という新たな環境に適応するために、家族システムを進化させ、その結果として、国家(や文字や法や・・)が誕生した。権威こそが、そのすべてを可能にしたのです。
◉人類は「満員の世界」への適応のために家族システムを進化させ、国家文明を築いた
③トッドは「権威」を理解していない
文字、国家、官僚等と直系家族の関連性を指摘し、シュメールにおける直系家族の成立を突き止めることで、上の仮説に必要な材料のすべてをわれわれに与えてくれたのは、もちろん、トッドです。
しかし、私はかねてから不審に思っているのですが、彼はどうも、直系家族の中の何が、どういう仕組みで、国家の誕生、文明の開花を可能にしたのかをうまく認識できていない。
歴史の始原において、権威こそが世界を変えたのだという事実を、十分に理解できていないようなのです。
先ほど引用した「アメリカ人は洗練されていないからこそ動物種として成功した」という趣旨の文章。彼は、それに続けて、次のように書いています。
他方、中東、中国、インドの父系制社会は、女性のステータスを低下させ、個人の創造的自由を破壊する洗練された諸文化の発明によって麻痺し、その結果、停止してしまった。
上 351頁
‥(中略)‥
直系家族は父系制レベル1であり、過剰な完璧さをもって規範に適合した人類学的典型となってしまわないかぎり、成長を加速させる力を持っている。イギリスには、フランス系ノルマン人に由来する直系家族的構成要素があった。実は米国にも ‥(以下略)
彼は、ひょっとして、権威を「自由を抑圧するもの」としてしか理解していないのではないか。私はそのような疑念を持っています。
「ほどほどの権威(=抑圧)は教育効果を高めるけれど、それを超えれば創造性を潰すことにしかならない」と。そうでなければ、西アジア、中国、インドの文明について、このようには書けないと思います。
しかし、人類が、人間を抑圧するために家族システムを進化させ、その創造性を抑えることで、5000年の歴史を紡いできた、などということがありうるでしょうか。
ですから、みなさん、いいですか。
ぜひとも、ここで覚悟を決めてください。
私たちは、権威の何たるかがわからないトッドにはまだ見えていない真実の領域に近づこうとしています。
この先、私たちは、トッドにも、他の西欧の知識人にも、頼ることはできません。
*西欧人を差別するわけではありませんが、多くの西欧の知識人にとって、核家族を客観視するのが容易でないことは事実だと思います。
私たちは、ついに、西欧と異なる家族システムを持っているからこそ容易に近づくことができる領域に分け入って、「近代」の真実を探り当てようとしているのです。
なーんてね。
ちょっと大袈裟になりました。
でも、本当。
私たちには、割と、簡単にわかっちゃうことなんです。
◼️ トッドとマクファーレン
現代の欧米諸国が見せる好戦性やレイシズムを「人間の本性」に結びつけて説明するとき、トッドは、彼が批判してやまないアラン・マクファーレンと似た過ちを犯しているように思えます。
イギリス人であるマクファーレンは、イギリスの個人主義(自由主義的な政治制度や経済のダイナミズム)と家族システム(核家族)との関連性に気づきながら、(トッドのいう)「英国人ナルシシズム」のあまり、そのすべてを、イギリスに固有の、歴史的産物とみなしました。
他方、トッドは、西欧近代の基礎にある核家族システムと狩猟採集民の家族システム(原初的核家族)の共通性に気づいたにもかかわらず、フランス人的普遍主義のゆえに、核家族に固有の特質を、全人類に共通の属性とみなしてしまうのです。
マクファーレンが「英国人ナルシシズム」に浸ることができたのも、トッドが「敵意原則」を人類普遍の原則とみなしてしまうのも、彼らが核家族の問題性、裏を返せば、核家族以外のすべての家族システムが保有する権威の重要性を理解していないからにほかなりません。
「西欧中心主義」といいたくなりますが、ひょっとすると、彼らの反応は、
「核家族(より未分化なシステム)の側が、進化した家族システムのメンタリティを追体験するのは極めて困難である」ということを示唆しているのかもしれません。
*逆は真ではない(マクドナルドのおいしさが万人に理解できるのと同じ)と私は見ていますが、どうでしょう。
④「権威」の効用
人類は、「満員の世界」に適応するために、家族システムを進化させ、権威の軸を生み出しました。
権威が発生したとき、人類が国家を形成することになった理由は単純で、そこに、人間が集まるための「中心」が生まれたからです。
何もなかった荒野に、柱が一本。
これが「権威」です。
せっかくの柱だから、旗でも掲げるとしましょうか。そうすれば、人々は、旗を中心に集まり、アイデンティティを形成することができます。旗印に照らして、何が正しいか、正しくないかを判断し、価値意識を共有することができます。旗を中心に、踊ったり歌ったりして、共に楽しみ、一体感を味わうこともできます。
中心に柱が一本ありさえすれば、敵がいなくたって、人間集団は一つにまとまることができるのです。
繰り返しますが、親族関係の体系化(=家族システムの構築)とは、「満員の世界」を生き抜くための、人類の適応です。
その第一段階で発生した権威の軸を、かりに人類の発明品とみるならば、それは人類史上最大の発明であったといってよいと思います。何しろ、歴史も、文字も、法も、国家も、みなこの一本の柱から始まったのですから。
かりに、権威の軸が生まれなければ、人類は、人口密度が上がると同時に「敵意原則」を活性化させ、戦いに明け暮れることになったでしょう。それでは、人類が、地球上で、増え、栄えることはできません。
だからこそ、人類は、「敵意の共有」以外の方法で、集団をまとめる方法を編み出した。人類は、権威の軸を支えに家族システムを構築することで、「敵意原則」を乗り越えたのです。
◉人類は、権威を軸とした家族システムの構築により、敵意原則を乗り越えた
新たな仮説に向けてー文明との遭遇
(1)第二の仮説
そういうわけなので、本講座は、問題含みの近現代の鍵を握っているのは核家族のメンタリティである、という前提を堅持します。
しかし、狩猟採集時代の原初的核家族は、権威は持っていなかったけれど、取り立てて暴力的でも好戦的でもなかったという。
ということは‥‥考えられるのは、こんな感じの仮説ではないでしょうか。
仮説② 原初的核家族が文明と出会ったとき、何かが起こった。
*近代だったら「絶対核家族」とか「平等主義核家族」ではないかとお思いの方がおられると思いますが、近代化の初期ないし直前の段階ではほとんどの地域はおそらく原初的核家族です。また、この講座では、トッドの立場に従い、絶対核家族と原初的核家族の相違を割と強調してお送りしてきましたが、最近の私は「両者の相違に本質的な意味はないのではないか?」「絶対核家族は原初的核家族が文明と出会って硬直化しただけではないか?」という疑念を持つようになっているため、以後、両者の区別が曖昧になり「核家族」とざっくりくくる部分が多くなると思います。ご了承ください。
ご存じのように、権威の誕生(直系家族の成立)から始まった家族システム(人間関係のシステム化)は、ユーラシア大陸の中心部では、その後も進化を続けていきます。
*こちらの連載で扱っています。
荒野に生じた一本の柱は、だんだん大きく豪華になって、遊牧民や商人が行き交う文明の中心地では、高くそびえる、豪壮な構造物に進化したわけです。
強大で威厳に満ちた権威の存在により、集団間の争いは平定され、まずは、地域一体を統一的に支配する帝国が生み出された。
そして、さらなる進化を経て、公明正大で気前よく、強さに加えて温かみや柔軟さをも持ち合わせた魅力的な権威に変貌すると、帝国は、さらに広範囲の人々を惹きつけ、緩やかに広がる世界帝国へと成長していった、と。
以上が、輝かしい「家族システムの進化」のストーリーですが、実は、ここには、これまで(本講座では)焦点が当たることのなかった「書かれざる歴史」も潜んでいます。
それは、文明の中心地であっても、家族システムの進化は満遍なく起こったわけではない、ということで、実際、アッシリア帝国の時代に至っても、周辺にはなお、原初的核家族の地域が残っていたのです。
*アッシリア帝国は、トッドによれば「女性の地位の最大限の低下を伴う」最強度の共同体家族の産物です。
*なお、アッシリアが「帝国」の名に相応しい国家であったのは、前10世紀から7世紀のいわゆる「新アッシリア時代」。そのため、この時期のアッシリアを「新アッシリア帝国」と呼ぶことがあります。しかし、「古アッシリア時代」「中アッシリア時代」「新アッシリア時代」の区分は歴史学の都合にすぎず、国家としてのアッシリアは、前2600年頃に都市国家アッシュルとして誕生したときから前609年頃に帝国の終焉を迎えるまで連続しているのだそうです。そうすると「新アッシリア帝国」の呼称はかえって誤解を招きやすいと私は思うので、本講座では単に「アッシリア帝国」と称することにさせていただきます(今回勉強するまで知らなかったので、この記事では「新アッシリア帝国」の語を用いています。すみません)(山田重郎『アッシリア 人類最古の帝国』(2024年、ちくま新書)参照)。
◉文明の中心地で家族システムが最大限の進化を遂げていたときも、近隣には原初的核家族地域があった
(2)狩猟採集民、アッシリア帝国の隣人となる
原初的核家族が文明と出会ったら、何が起きるか。ちょっと、想像してみましょうか。
かりに、原始時代の狩猟採集民の一群が、時空を超えて、アッシリア帝国の付近に飛んできたとします。元の場所に戻る術はない。つまり、彼らは、隣人として、帝国と共に生きていかなければならない運命です。
とりあえず、帝国の様子を見に行くと、そこには壁で守られた都市があり、壮麗な神殿、豪華な王宮、ほかにも様々な建造物があります。ひと目でそれとわかる姿の威厳ある王がいて、強大な軍隊、行政機構、法制度を司り、民を従わせ、広大な領土を治めている。聞けば、この国には1500年以上の歴史があって、歴代の王の事蹟は詳細に碑文に刻まれているのだとか。
宮殿の中には図書館があります。王が所有する粘土板には、文明発祥以来蓄積された知識のすべてが刻まれているそうです。収蔵書は、卜占(占いですね)に関するものが35%、祈祷や呪術や儀礼などの宗教関連が35%、残りは医学書、叙事詩、神話、歴史書、語彙表、辞書、数学書等の学術書で占められています。王は、偉大な君主であるためには、軍事面での強さだけでなく、あらゆる知識を身につけ、正しい判断、優れた行動に生かすことが必要と考えていたのです。
街に出れば、住民は、さまざまな職業に就き、日々の暮らしを楽しんでいました。
都市部では王宮と神殿を中心に、様々な職業の人々によって構成される複雑な階層社会が営まれた。宮廷官吏、祭司、占い師、呪術師、医師、預言者、歌手、楽人、商人、パン屋、ビール醸造人、料理人、菓子職人、搾油者、漁師、庭師、大工、鍛冶屋、石工、皮革加工者、衣服の仕立屋、家庭教師、書記、外交官、軍人など様々な職業人が暮らしていた。人々は、季節ごとに神殿を中心に催される祭礼に参加し、豊作、健康、安全を祈願し、非日常的な祝祭を楽しんだ。
山田重郎『アッシリア 人類最古の帝国』(ちくま新書、2024年)331頁
夫婦と子供のセットを基本に、何となく存在する親族集団を背景に、ひたすら柔軟な関係性の中で暮らしてきた狩猟採集の民は、この光景をどのように見るでしょうか。
彼らはまずは茫然と立ちつくし、やがて、ある者は荘厳な建築物に圧倒され、ある者は武人の隊列に目を見張るでしょう。物質的な豊かさに心を奪われる者がいれば、国王の権威に皆がひれ伏す様子に違和感を覚える者がいるかもしれない。しかし、何にせよ、彼らはここで生きていかなければなりません。
かりに、彼らのメンタリティの中に「権威」があったなら(例えば直系家族なら)、進んで王に帰順し、帝国の臣民として生きていくことを選ぶのではないかと思うのですが、そこは原初的核家族。
彼らは、「自由・自律・独立」といったものを、価値として認識してはいません(この点は近代以降の核家族とは異なります)。それらは、むしろ、習慣であり、彼らに染み付いた事実である。事実として「自由・自律・独立」を生きる民である以上、彼らが自ら帝国への服属を願うことはないでしょう。
帝国に服属しないとはどういうことか。それは、つまり、帝国の外で、帝国と伍していかなければならないということです。「システム以前」の狩猟採集民なのに‥‥
ど、どうしたらいいのでしょうか?
彼らは、家族システムを持っていませんが、ホモ・サピエンスとしての脳機能を備えていますから、おそらく、真似をすることはできるはずです。
彼らは、見よう見まねで、国家を作る。見よう見まねで、歴史を書き、法律を作り、王を立て、戦争をするでしょう。
彼らにとっては、どんな帝国の臣民にも劣らない脳機能(ホモ・サピエンスなので)が唯一の頼みの綱ですから、何より、文明発祥以来蓄積されたという学術知識を熱心に学び、研究もして、帝国文化に一気に追いつき、追い越そうとするでしょう。
そうして、彼らは、国を持ち、歴史書を持ち、法律を持ち、国王を持ち、学術に優れた、どこからどう見ても、立派な文明国家の国民だ、という風を身につけるでしょう。
でも、中身はどうでしょう?
どんなに上手に帝国を真似しても、彼らが「システム以前」の原初的核家族であるという事実に変わりはありません。
*これは、どんなに核家族の真似をしても、私たちが直系家族の民であるという事実に変わりはないのと全く同じです。
家族システムが未分化のままである以上、彼らのメンタリティは、基本的に、狩猟採集民のままなのではないでしょうか。
幸い、そして大変興味深いことに、彼らは、自らの手で、各種の文書をふんだんに書き残してくれています(たぶん、学術が頼りだからでしょう)。
原初的核家族が文明と出会うと、どういうメンタリティが形成され、それがどのように近現代につながっているのか。
次回に続きます!
◉文明との接触により開化を遂げたとしても、家族システムが未分化のままである以上、メンタリティに根本的な変化は起きないはずである
今日のまとめ
- 未開社会の原初的核家族はとくに暴力的・好戦的ではなかった
- 近代の核家族が原初的核家族に近いメンタリティを持つことは事実だが、それ自体が「抗争と掠奪」「暴力と殺戮」の要因とはいえない
- トッドは「集団の一体性は他の集団への敵意に依存する」という命題(敵意原則)を、家族システムを問わず全人類に妥当する公理と宣言するが、支持できない
- 親族関係の体系化(家族システムの進化)は「満員の世界」への適応であり、人類は「権威」の構築により敵意原則によらずに集団をまとめる方法を得て、国家文明を築き上げたと考えられる
- 「抗争と掠奪」「暴力と殺戮」につながるメンタリティは、「満員の世界」への適応を持たない核家族が文明と遭遇したときに生まれたものではないか(仮説)
